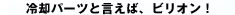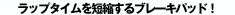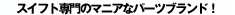_その他_
_その他_
日光テスト081211
2008年12月11日(木)
今、日光サーキットから帰ってきました。
今日は、ZONEブレーキパッドの開発で大変お世話になった、ARVOU(アルボー)さんの
走行会に便乗して、トーションビームの最終確認テストを行なってました。
途中、長谷川(弊社開発)が、ブッシュを反対向きに組んで、
望月さん(トーションビームの設計&製作者)に、こっぴどく怒られる事件はありましたが、
結果は◎。とっても良いテストとなりました。
では、このトーションビームの開発秘話を少しばかり。
FFと言えば、なんといっても、リアのロール剛性アップです。
しかし、田中の脳裏には、JTCCでみんなが使っていた、あの大根より太いスタビライザーの
イメージが強く、剛性を上げるといっても、かなり頑丈な物を作らなければなりません。
そこで、まず思いついたのが、トーションビームの下側開口部にスチールプレートを溶接して、
トーションビーム自体を強固なスタビライザーにするという方法でした。
この作戦で、リアのロール剛性はとんでもなく上がり、驚異のフロント接地を実現できました。
が、しかし、「ちと硬すぎる・・・」。サーキットでは抜群でも、ストリートの乗り心地が
あまりにも厳しい・・・・。
ということで、ほんの少しソフトな部分を持たせるため、この溶接部を、約40本のボルトナットで
固定するという戦略に出たのでした! こうすれば、ボルトの数でセットアップもできることになります。
「オレって、天才?」と、独り言をいいながら、本庄サーキットを連続で10ラップ。
最初は、狙い通り少しマイルドになり、十分にフロント接地も確保されていました。
これはいける!と思ったのもつかの間、ロール剛性はどんどんダウンしていく・・・、おかしい・・・・。
多少想像していたことではありますが、たった10ラップで、ボルトはすべて緩んでしまいました。
ZC31Sのトーションビームは、想像をはるかに超えてたわんでいるようです。
もちろん、リアのスタビライザーを強化する方法は、他にもいろいろありますが、やはり硬さが
調整できなければ、楽しくありません。
そこで、トーションビーム内に溶接にて固定されている純正のスタビライザーをくり抜き、
そこにスタビライザーのみ交換可能なブラケットを溶接する手法を取りました。
この方法だと、サーキットでリアのスタビライザーを交換するのに5分もあれば十分です。
最初にトーションビームを交換しなくてはならないことは、少々手間&コストがかかりますが、
交換後は、サーキットでセッティングに合わせて、瞬時にリアのロール剛性を変えられるメリットは、
やっぱ大きいと田中は思うのです。
サスペンションパーツの中でも、これほどまでに違いを感じられるパーツは他にはないと思いますので、
マニア?の方には、ちょ~、おススメの一品です。
サスペンション
商品撮影 その②
2008年11月27日(木)
今日はカタログ用の商品撮影を行ないました。
場所は、世田谷にある「尾山台スタジオ」。 もちろん、会社(弊社)の会議室です。
写真を撮ったのは、レース界では有名人の服部カメラマンです。
(こう見えても?レースの写真は凄いんですから)
リアスプリングからはじめたのですが、じつはこの商品を作るには、長い道のりがありました。
クルマのバランスが変わることから、「想定どおりにならないことが多いから」でした。
シングルレートタイプであることです。これで、あの、なんとも言えないフラット感が作り出せるのです。
アンダーステア傾向が強くなりますので、FFにとって、リアのストロークは、とっても重要なのです。
オリジナル リアスプリングのもうひとつのメリットは、荷重の変化や、路面からの突き上げに対して、
ゴツゴツしないことです。
しなやかさを持っていますので、サーキットとストリートの両立が可能となります。
現在、他社の車高調整式アタッチメントをすでに使用されている場合は、ほとんどのタイプで、このオリジナル リアスプリングの装着が可能となると思います。
うまく行けばという感覚で、お願いします。だって、そうすれば、
TM-SQUARE
エアインテークの位置は圧力が高い部分に!
2008年10月08日(水)
田中エアロプロジェクト?は、もちろん、カーボンボンネットも作ります。
最初は、ガッツリとアウトレットの空いたタイプを作ろうと思っていましたが、
ZC31Sの水温は、サーキットでもさほど上がらないことが発覚!
だったら、コスト的にもリーズナブルで作れる、純正形状にしようといきなり路線変更です。
でも、フレッシュエアを導入できるインテークはやっぱ欲しい。
特に、剥き出しタイプのエアクリーナーにすると、ちょうどラジエターの後方に位置するので、
吸入空気の温度が上がってしまいます。でも、インテークさえあれば、確実に吸入空気の温度は下がるハズです。
こうなると、同一体積中の酸素の数が多くなるので、充填効率ってものがよくなります。
これで、パワーが上がるという図式です。
まずは、エアインテークの位置決めからはじめました。
紙で形を作って(工場の中に某社のGTに使用したものがありましたので、ちょこっと拝借)、
一番効率が良さそうなところを探しました。
ちょっとマニアックな話ですが、ボンネットの前の方は、走行中、
かなりの正圧(圧力が高い)なのですが、真ん中あたりは、あまり高くない。
そして、ガラス周辺になると、またまた強い正圧となります。
だから、よく、ボンネットの後ろの部分を少し持ち上げて、隙間を作り、エンジンルームの
空気を抜こうとしている人がいますが、サーキット走行ではまったくの逆効果
(抜けるどころか入ってくる!)ですので、ご注意を。
話は戻って、エアインテークは、できるだけ正圧の強い部分で空けたいので、
エアクリーナとの位置関係を考慮しながらも、ほんの少し前で設定しました。
それから、写真のように純正のボンネットを切って形を作り、サーフェイサーで全体の形を整え、
型取り用とします。
後は、シッカリ型を作って、製品ができるのを待つばかりです。
なんだか、でき上がりが楽しみになってきましたが、スイスポのフロントバンパーを取外した
ルックスって、ターミネーターぽくって、カッコイイですね!
TM-SQUARE
リアバンパーは、こんな感じ です。
2008年10月03日(金)
リアバンパーも、いよいよ、ハードマスターに突入です。
計4ヶ所のエアアウトレット(空気の安売りとは訳しません・・・)と、少し後方にオフセットした
ディフューザー形状が、特徴です。(ちょうど、ナンバープレートの下あたりになりますが、
少し後方にディフューザーが飛び出しているのがわかるかと思います)
リアタイヤ後方のエアアウトレットは、リアタイヤハウス内の圧力を抜くのが目的となります。
今回のエアロは、インナーフェンダーが装着できる仕様ですので、この部分だけは、
インナーフェンダーに穴あけ加工が必要となります。
ドリルで穴を空け、ハサミか何かでチョキチョキとやってください。
また、ナンバープレート横のエアアウトレットは、かなり大きめなサイズとなっていますので、
リアバンパーが発生するドラッグをうまく抜いてくれます。
スーパー耐久を見ていると、接触等により、リアバンパーが脱落すると、ストレートが驚くほど速くなりますよね。
これは、まさにリアバンパーのドラッグが影響しているからです。
だから、最近のGTカーは、やたらリアバンパーが小さくなり、上部に装着されているのです。
あっ、それから、ASM金山氏のアドバイスで、ナンバープレートを付けたまま、バンパー交換ができるように、
ちょこっと加工が加えてありますので、封印を陸運局までもらいに行く手間も必要ありません。
そして、そして、こんな複雑な形状が、もちろん1ピースでできるハズもなく、当然のことながら、
2ピース構造となっております。あしからず・・・(もう、すでに居直りの領域?)。
-その他パーツ-
ホイールの色が決まらない!
2008年09月26日(金)
うぅ~ん、問題だ・・・。
色が決まらない・・・。何がって、ホイールの色ですよ。“イロ”。
現在の候補は、ホワイト、ガンメタ、ハイパーブラック、シルバー、ブラックポリッシュ、
そして、ガンメタポリッシュです。
もちろん、こんなにたくさんリリースしたら、在庫でお家が買えちゃいますので絞らねば。
できれば2色、MAXでも3色が限界です。
ホワイトは、どうしてもサーキットでは欲しい色なので、かなりの確率で当選確実と。
そうなると、やっぱり塗装してから表面に削りを入れる、ブラックポリッシュか、
ガンメタポリッシュとなるわけですよ。やっぱり。
じつは、エアロが形になる前に、ブラックポリッシュを純正のZC31Sにつけてみたんですよ。
そしたらね、もー、見た瞬間に、「うぉー、決まりだーっ」と確信が持てたのですが、
エアロができて、クルマがゴツゴツしてくると、洗練されすぎて力強さが・・・・・。
要するにポリッシュ系は、削った表面以外が、黒っぽくなって、視界から消えるのです。
この効果で、スポークが細く見えるのですが、ドハデなエアロが付くと、
ちょっと筋肉が足りない感じになるんですよ。
その点、リム部までバッチリ主張するシルバーは、やっぱ「筋肉モリモリ」で、
エアロとはマッチングするんですよ。
エアロが付いていないなら、ポリッシュ系の「洗練された上品さ」がドンピシャ!でくるのですが、
エアロが付くと、もう少し筋肉質の方が良く似合う・・・。
いや~、どうしよう・・・。
両者とも、捨てがたい・・・。でも、決めなきゃ・・・。
と、思っていると、また夜中の12時だ・・・・・。
エンジン
バージョン2のコンプリートエンジン完成!
2008年09月25日(木)
2008/09/25
キーワード
バージョン1のエンジンで、約20000kmの走行を終え、
信頼性に確信が持てたので、もう少し圧縮を攻めた仕様のバージョン2が、いよいよ完成しました。
芹沢さんの、「教頭、できたよ~」の電話で、一路新幹線で静岡へ。
(でも、なんでスクールでの役職?で呼ばれてんだ??)
工場に着いたら、もうすでに、バージョン2エンジンは載せ替えが終了しており、
冷却水の注入中でした。もちろん、使用したのは、BILLION SUPER THERMO LLC タイプ PG プラスです。
(誰だー、ミノル汁って言ってるヤツは!)
BILLIONの冷却水
その後、一発でエンジンもスタート。
しばし、エンジンが暖まるまで待ってはみたものの、冷却ラインのエアがうまく抜けない・・・。
芹沢さんの話によると、ZC31Sは、冷却ラインのエアがかなり抜けにくいらしく、
必殺技を教えていただきましたので、皆さんにもお伝えしておきましょう。
エア抜きの方法は、ちょうどブレーキフルード注入口の下あたりに位置する、細いホースを
抜き、そこからエア抜きを行ないます。エンジンをかけた状態で、ロアホースをパフパフしな
がらこの作業を行なえば、かなり短時間でエア抜き完了です。
無事エンジンの載せ換えも終了し、その後、慣らし運転のレクチャーも受けました。
だいたい、慣らし運転って、クソめんどくさくって大っ嫌いな私は、
「レーシングカーで、慣らしなんてやったことがないのに、なんで、慣らし運転が必要なの?」と、聞いてみると、
「あのね、あんたたちドライバーが乗る前に、レーシングエンジンはベンチの上で、ガソリンをドラム缶何本も使って、
我々エンジン屋が慣らしをやってるの」と、もっともらしい答えが。
そりゃそうですよね。
フォーミュラカーが、走行中にエンジンの慣らしなんかやってたら、カッコ悪いだけじゃなく、危ないもんね。
田中、すごーく納得でした。
で、芹沢式、慣らし運転の極意?は下記のとおり。
4000rpm以下 500km
5000rpm以下 200km
6000rpm以下 100km
合計、800kmの走行が、慣らし運転として必要だそうです。
作業終了後、静岡の街をオッサン2人で試乗に出ました。
トルクの太り方はバージョン1と同じものの、やっぱり圧縮を少し上げただけで、
「高回転域のパンチがかなり良くなってる!」と、私が嬉しそうにコメントすると、なんだか芹沢さんの顔が怖い。
「ハイハイ、4000rpmでしたね・・・・・」。
それから、工場に帰り、一緒に食事に出掛けて、東名で東京まで帰ってきました。
大きな声では言えませんが、やっぱり、高回転のパンチはなかなかです・・・。
TM-SQUARE
やっぱ、こっちだよな~。
2008年09月22日(月)
ここで問題が発生しました。
問題とは、ダウンフォースを追ために、フロントバンパーの形状が二転三転したことで、
どうも、サイドステップとのバランスが悪くなってきたように思えるのです。
要するに、フロントバンパーの凹凸に対して、どうもサイドがスッキリしているというか・・・。
そこで、心機一転、サイドステップをゼロから作り変えてみました(また、お金が・・・・・)。
そうです、田中は妥協するのが大嫌いなのです。エアロ製作者や、社員から冷たい視線を
浴びても、気に入るもの、納得できるものしか作る気にはなりません。
と、言うことで、こんな形状にしてみました。ジャジャ~ン!
新型サイドステップ!!

やっぱ、こっちですよね。
これなら、ダウンフォースに影響するフラットな下面を広く取れるようになります。
そして、何よりもドア付近の乱流を下面に入れることなく、シッカリせき止めてくれそうです。
どうです、カッコいいでしょ!
でもね、またまた、大問題です。
じつは、このサイドステップの形状では、ひとつの型から抜けなくなってしまうのです。
でも、この形状はレーシングカーではあたり前だし・・・、うぅん・・どうしても妥協できません・・・。
で、もってどうしたかというと、得意の2分割しかありません!
下側が割れても交換できるし(もういいか・・・)。
ということで、TM-SQUAREのサイドステップは、めでたく?上下2分割の仕様として発売します。
(やっぱり、機能に妥協はできませんでした・・・)
あと、一点ご注意があります。
それは、このフラットアンダーパネルの飛び出しを製品ではもっと大きくとろうと思っています。
もちろん、その方が効果が高く、全幅もこのあたりはかなり内側に絞り込まれていることか
ら、広くならないのですが、注意があるのです。
それは、乗り降りするときに、意識しないと踏んでしまうのです。
恐らく、クルマの所有者は、すぐに慣れるので問題ないと思いますが、同乗者には、必ず乗り降りの前に、言ってほしいのです。
でないと、田中が作ったサイドステップで彼女と別れたなんて、あとで言われても、責任取れませんから・・・。
そこんとこ、ホントよろしくお願いしますね。
TM-SQUARE
ASM 金山氏 のアドバイス
2008年08月26日(火)
7月のはじめに、以前から仲良くしていただいている、
ASM 金山氏と一緒にエアロを作っている工場に行く機会がありました。
ASMのエアロは、かなりダウンフォースを求めた形状となっていますので、空力マニア同士、
いや、エアロパーツの先輩として、アドバイスをいただければという、私の下心です。
その、アドバイスの中に、純正のフォグライトは、「絶対付けたいユーザーがいる!」という、
金山氏のアドバイスを受けて、早速、形にしてみました。
また、せっかく大きな開口部に、オプションパーツとして取付けるわけですから、
ブレーキやエンジンルームに簡単にフレッシュエアが導入できるように、エアインテークを
装備し、後方に50φのダクトが接続できるように作り込みを行ないました。
現状では、まだ色が付いていませんが、バンパー本体をボディと同色にして、
インテークパネルを黒に塗り分けると、かなりカッコよくなると私は思っています。
自分で言うのもなんですが、ちょっと、ヨーロッパの香りがしてきませんか!
TM-SQUARE
フロント バンパーの形状
2008年08月09日(土)
やっぱ、人生も恋愛も出会いって、大切ですよね。
じつは、ダウンフォースにも出会いはとっても大切なのです。
ここで言う出会いとは、空気との出会いですので、フロントバンパー部の形状は、
とても重要だということです(強引って言わない!)。
まず、有効なダウンフォースを発生できる、ボディ下面にはできるだけ整流された空気を、
速度の速い状態で取り込みたい。そのためには、ボディ前面に当たった乱流が下面に入り込まないように、
バンパーの先端はちょっと飛び出した形状が望ましくなります。
また、この部分が飛び出すことで、ダウンフォースの発生源である、アンダーパネルが前後方向に長くなる
こともメリットとなります。
また、フロントコーナー部の形状は、最先端のノウハウがたくさん投入されています。
たとえば、上記写真の開口部、右側の形状は、通常の形状とは違い、逆Rになっています。
通称、工藤静香 形状!(だれだ、古いって言ったヤツ)。
これは、フロントコーナーに当たった空気を、勢い良く外側に向けるための工夫です。
ここで、空気を外側に角度をつけた状態で排出できると、あら不思議、フロントタイヤハウスの空気を
引き出してくれるのです。
まぁ、このあたりのことは、WEBサイト内にもバッチリ書くと思いますので、解説は乞うご期待ということで。
しかし、この形状を実現するには、大きな問題があります。
それは、バンパー本体とアンダー部を2分割で作るしか方法がないことです。
当然GTカーでは2分割で作っていますが、コストは無視ですよね・・、競技車輌ですから。
でも、2分割にすれば、バンパーを2つ作るのと同じコストが、型代にも製品コストにもかかってくるのです。
でも、こんな形状のものを1つの型から造るのは不可能だし・・・・・。
このフロントバンパーを市販するにあたって、本当にコストのことは考えました。
でもね、やっぱりここで妥協したら、面白いものなんて作れないと思うんですよ。
どーせ、趣味ではじめたプロジェクトだし、田中の考える面白さに共感してくれる人だけが買ってくれると
思いますので、思い切って2分割にしてみました。
そうだ、2分割だからこそのメリットもありますよ。
それは、アンダー部を破損した時、バンパー本体は生き残っていたら、パーツとしてアンダー部だけが買える!
ま、たいしたメリットじゃないかも知れませんが・・・。